定義と背景
IHD は、冠動脈の血流が心筋の酸素需要を満たせなくなることで起こる疾患群です。病因の約9割はアテローム硬化性プラークと血栓形成ですが、冠攣縮や微小循環障害(INOCA)でも虚血は生じます。世界の死亡原因の首位を占め、日本でも年間約7万人が急性冠症候群で入院しています。- 世界の死因トップ
2019 年の循環器疾患死亡 1,860 万人のうち、9.1 百万人が IHD。全死亡の 16 % が IHD によるもの - 日本の状況
急性心筋梗塞入院は年間 7 万例前後。STEMI 比率は 55–60 % で横ばい、平均 30 日死亡率はおよそ 5 %。
病態生理の要点
- プラーク形成:LDL コレステロールが内膜に沈着 → 炎症・線維化 → プラーク成熟
- プラーク破綻/びらん:血小板凝集と凝固活性化で血栓が急速に成長
- 供給‐需要ミスマッチ:重度貧血や頻脈でも虚血は増悪(“タイプ2 MI” の概念)
臨床分類(JCS 2022 )
| 大分類 | 代表病型 | 病態キーワード | 再灌流目標 |
|---|---|---|---|
| 慢性冠症候群(CCS) | 労作性狭心症 | 固定狭窄+酸素需要↑ | 症状/虚血が残れば PCI/CABG |
| 冠攣縮性狭心症・微小循環障害(INOCA) | 冠れん縮・微小血管不全 | Ca 拮抗薬 + 硝酸薬。PCI 効果は限定 | |
| 急性冠症候群(ACS) | 不安定狭心症 (UAP) | 胸痛持続<→酵素陰性 | ≤12 h で侵襲的評価(高リスク即時) |
| NSTEMI | 酵素陽性・ST 非上昇 | PCI 24 h 以内 (高リスク 2 h) | |
| STEMI | ST 上昇+酵素陽性 | 発症→再灌流 ≤90 min が鉄則 |
リスク因子と予防目標
- 修正不可能:高齢・男性・家族歴・早発 IHD の既往
- 修正可能:高血圧、脂質異常症、糖尿病、喫煙、肥満、CKD、睡眠時無呼吸など
- ガイドライン目標
- LDL-C <55 mg/dL(超高リスク<40 mg/dL)
- 収縮期血圧 120–130 mmHg、HbA1c <7.0 %
- 運動:150 分/週の中強度有酸素+レジスタンス
臨床症状
| 病型 | 典型症候 | 留意点 |
|---|---|---|
| 労作性AP | 運動・情動で前胸部圧迫痛(2–10 分) | 安静・ニトロで速やかに消失 |
| 冠攣縮性AP | 夜間・早朝の安静時、ST 一過性上昇 | 喫煙・寒冷・アルコールが誘因 |
| ACS | 20 分以上持続する胸痛、冷汗、吐き気 | 糖尿病・高齢者では無痛虚血に注意 |
診断アルゴリズム
- 初期検査
12 誘導 ECG(ST 変化)+ 高感度トロポニン 0-1 h ルール - 非侵襲的検査
- 運動負荷 ECG/SPECT/Stress-MRI
- 冠 CT–FFR:解剖と機能同時評価
- 侵襲的評価
- 冠造影+FFR ≤0.80 or iFR ≤0.89 → 機能的有意狭窄
- IVUS / OCT:プラーク種類・ステント最適化確認
- リスク層別化スコア
- TIMI / GRACE:死亡・再 MI 予測に必須
治療戦略
慢性冠症候群
- 至適薬物治療(OMT)
- 抗血小板:アスピリン 75–100 mg
- 抗狭心症薬:β遮断薬→Ca拮抗薬→長時間作用硝酸薬
- 予後改善薬:スタチン、ACE I/ARB、SGLT2 阻害薬(糖尿病/HF 合併)
- 再血行再建の適応
- 症状コントロール不良、広範虚血、左主幹部病変(低リスク外科なら CABG 推奨)
薬剤(OMT)
| カテゴリ | 主要薬剤 | 予後改善エビデンス |
|---|---|---|
| 抗血小板 | アスピリン ± P2Y12 阻害薬 | DAPT 12 か月で MACE↓ |
| 脂質低下 | 高強度スタチン、PCSK9 阻害薬 | LDL-C 1 mmol/L↓で再発 22 %↓ |
| 虚血緩和 | β遮断薬 → Ca 拮抗薬 → 長時間硝酸薬 / ラニジピン | 胸痛緩和・運動耐容能↑ |
| 予後薬 | ACE I / ARB、MRA、SGLT2 阻害薬(糖尿病・HF) | 心血管死・HF 入院↓ |
血行再建の適応
| エビデンス | デザイン | 主な結論 |
|---|---|---|
| ISCHEMIA 2020 | 中等度以上虚血 5,179 例:PCI/CABG vs OMT | 有意な死亡・MI 減少なし(4 年) → 症状負荷例で有用 |
| FAME II | FFR ≤0.80 病変で PCI 追加 | PCI 群で不安定狭心症・再血行再建↓ |
| SYNTAX | 3 枝/LMT 病変:PCI(1G DES) vs CABG | CABG が MACE 低率 (5 年) → SYNTAX スコアで選択 |
- SYNTAX ≤22+2 枝以下 → PCI 有利
- LMT + 多枝/SYNTAX >22 → CABG が推奨
急性冠症候群
- 初期対応:“MONA”+抗凝固(ヘパリン)
- 再灌流
- STEMI:一次 PCI を発症→90 min 以内に完了。不可なら速やかに血栓溶解→救済 PCI。
- NSTEMI/UAP:GRACE/TIMI 高リスクなら 24 h(極高リスクは 2 h)PCI。
- 薬物
- DAPT:アスピリン+P2Y12 阻害薬(12 か月)
- 高強度スタチン(LDL-C <55 mg/dL)
- β遮断薬、ACE I/ARB、MRA(EF ≤40 %)
特殊病態
- INOCA(非閉塞性冠動脈虚血):冠攣縮、微小循環障害を含む。対症療法+リスク管理が中心。
- MINOCA(心筋壊死だが閉塞なし):冠微小塞栓、冠攣縮、心筋炎等を鑑別。
- タイプ2 MI:貧血、頻脈、低血圧など供給不足が主体。基礎疾患の是正が重要。
| INOCA | MINOCA | 冠攣縮性 AP |
|---|---|---|
| 「虚血あり・閉塞なし」 | 「壊死あり・閉塞なし」 | ST 上昇発作、アセチルコリン試験陽性 |
| 微小血管機能検査(IMR、CFR)が鍵 | 心エコー・MRI で心筋炎等を除外 | Ca 拮抗薬+禁煙必須 |
合併症・予後
- 急性期:心原性ショック(7 %)、致死性不整脈、乳頭筋断裂
- 慢性期:HFpEF から HFrEF まで心不全移行率 20 %
- 5 年死亡率:STEMI で 15 %、NSTEMI で 25 %(高齢・腎障害で上昇)
二次予防と心臓リハビリ
- LDL-C <55 (超高リスク <40)/血圧 120–130/HbA1c <7
- DAPT 12 カ月後はアスピリン継続 ± デエスカレーション
- 心リハ:有酸素 + 抵抗運動を週 3–5 回、メタ解析で全死亡 25 %↓
- デジタルヘルス:スマートウォッチによるリズム監視、オンラインリハ介入の有効性も報告
まとめ
- CCS vs ACS を瞬時に判別:時間軸で使う検査・治療が変わる。
- “発症→90 分” は STEMI の生命線:システム対応を最適化。
- OMT を怠らない:抗血小板+最強スタチン+リスク因子修正。
- 再血行再建は機能的・解剖学的評価で個別化:FFR/iFR、SYNTAX スコアを活用。
- 二次予防=長距離走:LDL-C と運動療法で再イベント&死亡を大幅に減らせる。
PCIトップページ
MEトップページ
参考
https://www.j-circ.or.jp/cms/wp-content/uploads/2023/03/JCS2023_fujiyoshi.pdf?

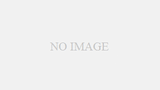
コメント