このページでは、心臓カテーテル検査の仕組みや原理について紹介します。
心臓カテーテル検査とは
X 線透視下で直径 1.5〜2 mm のカテーテルを末梢動脈・静脈から心臓内へ進め,
血行動態計測 と
造影/画像診断,さらに
経皮的治療(PCI など) まで行う。冠動脈疾患のゴールドスタンダードであり,右心系評価・重症弁膜症術前評価でも不可欠である
“侵襲的診断”が必要なのか
非侵襲的イメージング(CCTA、CT-FFR、Stress-MRI など)が急速に洗練されたとはいえ、
病変の形態・血行動態・微小循環まで同時に可視化できるのはカテーテル検査だけです。
- 冠動脈のグレーベース(50–90 % 狭窄)
- 多枝・左主幹部病変で revascularization 戦略を決める場面
- 肺高血圧・シャント・弁膜症の確定診断
診断カテーテルのラインナップと測定パラメータ
| 検査 | 目的/測定項目 | カットオフ・診断基準 |
|---|
| 冠動脈造影 (CAG) | 狭窄率・石灰化・分岐解剖を 2D/3D で可視化 | 有意狭窄:直径狭窄率 ≥50 % |
| 左室造影 (LVG) | EF・局所壁運動・MR 定量 | EF <50 % で収縮不全 |
| FFR(Fractional Flow Reserve) | 超重症狭窄の機能的意義 | ≤0.80 で虚血性と判定 |
| iFR(Instantaneous wave-free Ratio) | 安静時指標、薬剤負荷不要 | ≤0.89 が等価閾値 |
| CFR(Coronary Flow Reserve) | 巨視的+微小循環複合指標 | <2.0 で低下 |
| IMR(Index of Microcirculatory Resistance) | 純粋な微小血管抵抗 | ≥25 U →微小循環障害、≥40 U は重症 |
| IVUS / OCT | プラーク性状(石灰化・薄いキャップ)/ステント最適化 | 最低管腔面積 (MLA) <4.0 mm² は虚血疑い |
| 右心カテーテル (RHC) | RAP・mPAP・PCWP・PVR を測定 | mPAP ≥25 mmHg + PVR >3 WU で肺高血圧 |
分類と概要
| 系統 | 検査(略語) | 測定/可視化できる項目 |
|---|
| 左心系 | CAG | 冠動脈解剖・狭窄率 |
| LVG | 左室 EF・壁運動・MR 定量 |
| FFR/iFR | 狭窄の機能的意義 (FFR≤0.80) |
| IVUS / OCT | プラーク形態・ステント最適化 |
| 右心系 | Swan–Ganz (RHC) | RAP・mPAP・PCWP・CO (Fick/TD) |
| RVG | 右室 EF・TR 定量 |
| 特殊 | 心筋生検 | 心筋炎・遺伝性心筋症の確定診断 |
| IMR / CFR | 微小循環機能(INOCA 診断) |
アクセスルートとデバイス
| ルート | 利点 | 注意点 |
|---|
| 橈骨動脈 (TRA) | 止血容易・早期離床・出血 50–60 % 減 | スパズム → 事前ニトロ+Ca 拮抗薬 |
| 尺骨動脈 | TRA 不可時の代替 | 解剖変異多・穿刺難度↑ |
| 大腿動脈 | 太径デバイス (IABP, Impella, TAVI) | 後出血・偽動脈瘤に留意 |
| 頚静脈/大腿静脈 | RHC, EPS | 空気塞栓防止の水封管理 |
シース選択6 Fr が標準。IVUS/OCT+ロータなら 7 Fr,Impella CP は 14 Fr シースが必要。
前処置・周術期管理
- 抗血小板/抗凝固:CAG 単独ならアスピリン継続。予定 PCI は DAPT 開始。
- 腎保護:Cr>1.5 mg/dL なら生理食塩水 1 mL/kg/h + 低浸透圧造影剤。
- 造影アレルギー:ステロイド+H1/H2 ブロッカー 13 h, 6 h, 1 h 前プレメディ。
- 鎮静:ミダゾラム 1–2 mg iv を基本。高リスクは麻酔科管理も検討。
- 放射線対策:患者 DAP 5 Gy 超で皮膚傷害リスク → 角度変更・フレームレート 7.5 fps。
手技フロー – 左心カテーテル(例:冠動脈造影+FFR)
- 穿刺・シース挿入(TRA 6 Fr)
- ヘパリン化:100 IU/kg、ACT 250–300 s を維持
- ガイディング挿入 → CAG(左右 30°/0°、RAO 30°/CAU 20° など 6–8 投影)
- 病変選定 → 圧ワイヤ通過
- ドリフトゼロ → FFR 計測(アデノシン 140 µg/kg/min)
- PCI が必要なら バルーン前拡張 → DES 留置 → OCT でステント apposition・MLA 確認
- 止血:TRA は TR Band で 2 h グラデュアルリリース
- 解析レポート:SYNTAX Score/FFR 値/造影量/DAP を記載
4-1 冠動脈造影(CAG)
- 投影法:
- LCA:RAO 30°/CAU 30°、LAO 50°/CRA 20°
- RCA:LAO 30°/CRA 0°、RAO 30°/CAU 20°
- 造影:1 投影 4–6 mL、fps は診断のみなら 7.5–10 fps に下げ被曝を削減。
- QCA:ダイナミックレンジ 12bit 以上で自動狭窄解析→ 経時比較に有用。
4-2 FFR/iFR
- ワイヤ校正 → ドリフト≦3 mmHg を必ず確認。
- アデノシン投与:末梢静脈 140 µg/kg/min(腎障害ならニコランジル 0.2 mg/kg bolus 代替)。
- ハイブリッド戦略:iFR 0.86–0.93 の “グレーゾーン” → 追加 FFR がエビデンスベース
4-3 微小循環評価(IMR/CFR)
- Thermodilution:3 回平均で 30 % 以上乖離する場合は再測定。
- IMR ≥25 U でも CFR >2.0 ならエピ狭窄寄与が大きいと判断し PCI が優先。
4-4 右心カテーテル(RHC)
- サーモダイリューション CO:5 % 以内誤差で 3 回平均
- Shunt (Qp/Qs):O₂ step-up を段階計測、Qp/Qs ≥1.5 が手術適応(ASD,VSD)。
合併症とリスク管理(診断カテ限定)
| 合併症 | 発生率 | 予防/初期対応 |
|---|
| 穿刺部出血・血腫 | ≈1 % (TRA) | TRA+小径シース+ACT<250 s |
| CIN(造影腎症) | 1–2 %(CKD10 %) | 造影量管理・水和・低浸透造影剤 |
| 心室細動(ガイド脱落時) | 0.1 % | 即バルサルバ解除→DC |
| 放射線皮膚障害 | <0.05 % | DAP>5 Gy でアラーム→角度/距離変更 |
ガイドライン
- JCS 2022 Stable CAD フォーカスアップデート
- CCTA を“第一選択”に格上げ。ただし高石灰化・不整脈では CAG が依然 gold standard。
- ESC 2023 Radial Access Consensus
- TRA は出血・死亡を有意に低減。全 STEMI でクラス I 推奨。
- FAME 3 (2021) FFR ガイド PCI vs CABG
- 3 枝病変で MACE 差なし。ただし再血行再建は PCI 群で多い。
- Outpatient Cath Study (2023)
- 外来 CAG+PCI は出血・再入院率に差なくコスト 20 % 減
知っておくべき数値
| パラメータ | 正常範囲 | 虚血・異常閾値 |
|---|
| FFR | 0.81–1.00 | ≤0.80 |
| iFR | 0.90–1.00 | ≤0.89 |
| CFR | >2.5 | <2.0 |
| IMR | <25 U | ≥25 U(重症≥40 U) |
| mPAP | 8–20 mmHg | ≥25 mmHg(PH) |
| PCWP | 6–15 mmHg | >15 mmHg(左房圧上昇) |
| Qp/Qs | 1.0 | ≥1.5(介入適応) |
まとめ
- 心臓カテーテル検査は“診断+治療+機能評価”の総合ツール。
- アクセスは橈骨動脈が基本—出血・早期離床のメリット大。
- 合併症は血管・腎障害・放射線―予防策を手技に組み込む。
- “非侵襲 → 機能評価 → 個別最適治療”へ移行。
——————————
右心カテーテル検査とはMEトップページ

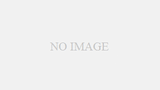
コメント